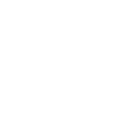Beauty clinic
美容クリニック総研
【五感が整う空間デザイン・シリーズ②】
香りで記憶に残る空間 ― 嗅覚がつくる“また行きたい”の感情
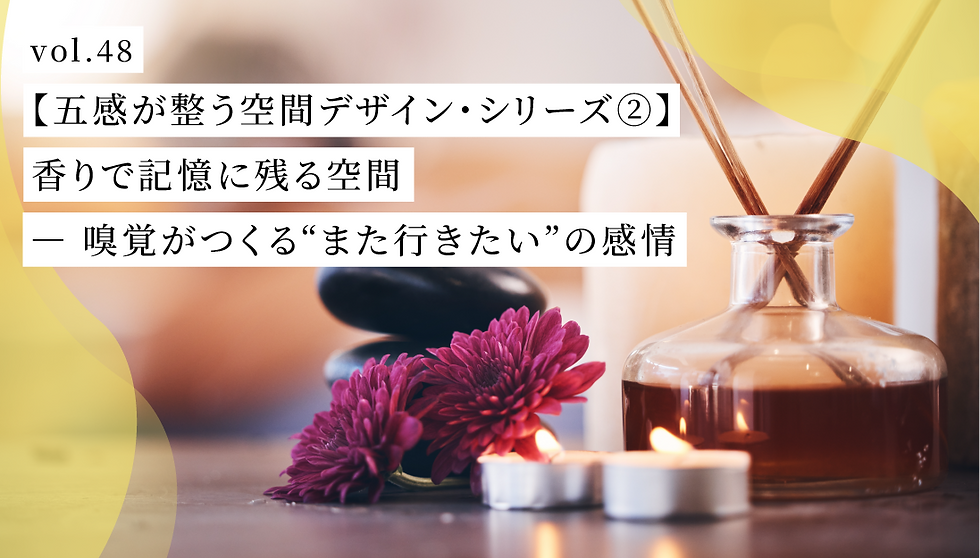
最終更新日:2025/12/5
著者:
所長 石田 毅
導入文 中国人、とりわけ中国人富裕層の中で、日本への医療ツーリズムに高い将来性があると言われています。
では、中国人富裕層が、わざわざ日本に医療観光に来る理由とは何でしょう?
その理由は、中国と日本の医療システムを比較してみるこ��とで明らかになります。そこにはいくつかの重要な違いが存在します。
中国では、病院の数が慢性的に不足しており、特に地方では医療レベルに大きな差が存在しています。この差は都市部と地方の医療サービスの質において顕著で、高い医療を求める人々が都市の病院へと集まることで、大混雑を引き起こしています。
さらに、中国の医療体制では歩合制が導入されている場合があり、医療費が非常に高額になる傾向があります。
空間に漂う香りは、風景を記憶に残すスイッチとなることがあります。 人が「またこの場所に来たい」と思うとき、視覚や音だけでなく、嗅覚が深く関わっていることが多いのです。 本記事では、香りが人の心理と記憶にどのように作用するか、そして空間設計として香りをどう取り込むかを、科学的視点から整理して解説します。
Ⅰ|香りが人の心理に作用する理由
嗅覚は他の感覚と異なり、直接大脳辺縁系に信号を送ります。通常、視覚や聴覚などの情報は中間を経て処理されますが、香りは嗅覚神経 → 嗅球 → 海馬・扁桃体といった「記憶・感情中枢」にダイレクトにつながっているのが特徴です。
この経路の直接性ゆえ、香りは瞬時に�感情や記憶を揺さぶる力を持ちます。また、香り刺激が適切な濃度で与えられると、ストレス指標の低下や心拍安定などの生理反応が観察される研究もあります。
Ⅱ|香りが“体験記憶”を設計する仕組み
香りが記憶と結びつく現象として有名なのがプルースト効果。ある香りが過去の記憶を瞬時に呼び起こす体験を多くの人が経験します。このように、香りは時空を超えて体験を呼び戻す触媒となるのです。
空間との香りの結びつきが強いほど、記憶は深く刻まれます。たとえば来院の導線・滞在時間・場所(受付→待合→診察室)が香りでつながれていると、その体験が「香り付きの記憶」として残りやすくなります。つまり、香りは体験価値の記憶化装置として作用します。
Ⅲ|香りをデザインする際のポイント
香り設計にあたっては、以下の要素に注意が必要です:
香気強度と拡散距離:強すぎると不快、弱すぎると効果が伝わらない
立ち上がりと切れ方:シーン転換時に香りが急激に変化すると違和感を生む
嗜好性の調整:香りの好みは人によって異なるため複数香調のバリエーションを検討
持続性・揮発特性:香り持続時間、湿度や温度による揮発変動
香りの“モーメント設計”:来院者が香りを印象的に感じる場所(入口/待合/診察前など)を意図的に設計する
香り設計は単なる香料選定ではなく、環境の時間構成と体験導線を整える行為と言えます。
Ⅳ|まとめ|香りが信頼を紡ぐ理由
香りは、空間の記憶をつくる見えない筆跡です。適切な香り設計は、安心感を心理��的に補強し、再来意欲を高める力を持ちます。香りを空間体験の記憶に変える工夫こそ、CXデザインの中で無視できない要素なのです。
◼︎CLINIC総研所長 石田のコメント
美容クリニックを問わず、デンタルクリニック、内視鏡クリニックなど、「クリニック」と名が付く場所は、往々にして喜び勇んで行く場所ではない。美容クリニックは時代の変遷とともに訪れる際のハードルは下がってきているものの、まだまだ「緊張」がつきまとう場所であることは間違いない。
そのような空間では「緊張している患者さんをそれ以上緊張させない」ことが重要になる。リラックスとまではいかなくても、交感神経優位=緊張にならないような体験設計が重要だ。今回は「五感が整う空間デザイン・シリーズ」の第2弾として「香り」を取り上げた。
現代における香りの代表格は「アロマ」ではないだろうか。ホテル、商業施設、個人宅などなど、アロマの香りが活用されている場所は数限りないし、「アロマ」という言葉を聞かない日はないくらい、アロマが現代では浸透している。
では、数あるアロマの香りの中でも「リラックス」という観点で効果が期待できる種類は何になるのだろうか?
内閣府に公益認定された、アロマテラピー関連で唯一の公益法人「AEAJ」の調査によると、リラックスのために多くの機会で活用されているのが、「ラベンダー」と「サンダルウッド」であることが分かりました。

ラベンダーは、主成分である「リナロール(linalool)」「酢酸リナリル(linalyl acetate)」が中枢神経系に作用して副交感神経を優位にすることが分かっています。鼻から吸収された香気成分が**大脳辺縁系(特に扁桃体・海馬)**に作用し、ストレス反応を抑制するともいわれます。
また、サンダルウッドは、主成分の「α-サンタロール(α-santalol)」「β-サンタロール」が嗅覚を介してGABA受容体やセロトニン経路に作用し、鎮静・抗不安効果をもたらす可能性があるとされます。
クリニックナレッジvol.48
所長 石田 毅
空間に漂う香りは、風景を記憶に残すスイッチとなることがあります。 人が「またこの場所に来たい」と思うとき、視覚や音だけでなく、嗅覚が深く関わっていることが多いのです。 本記事では、香りが人の心理と記憶にどのように作用するか、そして空間設計として香りをどう取り込むかを、科学的視点から整理して解説します。
Ⅰ|香りが人の心理に作用する理由
嗅覚は他の感覚と異なり、直接大脳辺縁系に信号を送ります。通常、視覚や聴覚などの情報は中間を経て処理されますが、香りは嗅覚神経 → 嗅球 → 海馬・扁桃体といった「記憶・感情中枢」にダイレクトにつながっているのが特徴です。
この経路の直接性ゆえ、香りは瞬時に感情や記憶を揺さぶる力を持ちます。また、香り刺激が適切な濃度で与えられると、ストレス指標の低下や心拍安定などの生理反応が観察される研究もあります。
Ⅱ|香りが“体験記憶”を設計する仕組み
香りが記憶と結びつく現象として有名なのがプルースト効果。ある香りが過去の記憶を瞬時に呼び起こす体験を多くの人が経験します。このように、香りは時空を超えて体験を呼び戻す触媒となるのです。
空間との香りの結びつきが強いほど、記憶は深く刻まれます。たとえば来院の導線・滞在時間・場所(受付→待合→診察室)が香りでつながれていると、その体験が「香り付きの記憶」として残りやすくなります。つまり、香りは体験価値の記憶化装置として作用します。
Ⅲ|香りをデザインする際のポイント
香り設計にあたっては、以下の要素に注意が必要です:
香気強度と拡散距離:強すぎると不快、弱すぎると効果が伝わらない
立ち上がりと切れ方:シーン転換時に香りが急激に変化すると違和感を生む
嗜好性の調整:香りの好みは人によって異なるため複数香調のバリエーションを検討
持続性・揮発特性:香り持続時間、湿度や温度による揮発変動
香りの“モーメント設計”:来院者が香りを印象的に感じる場所(入口/待合/診察前など)を意図的に設計する
香り設計は単なる香料選定ではなく、環境の時間構成と体験導線を整える行為と言えます。
Ⅳ|まとめ|香りが信頼を紡ぐ理由
香りは、空間の記憶をつくる見えない筆跡です。適切な香り設計は、安心感を心理的に補強し、再来意欲を高める力を持ちます。香りを空間体験の記憶に変える工夫こそ、CXデザインの中で無視できない要素なのです。
◼︎CLINIC総研所長 石田のコメン�ト
美容クリニックを問わず、デンタルクリニック、内視鏡クリニックなど、「クリニック」と名が付く場所は、往々にして喜び勇んで行く場所ではない。美容クリニックは時代の変遷とともに訪れる際のハードルは下がってきているものの、まだまだ「緊張」がつきまとう場所であることは間違いない。
そのような空間では「緊張している患者さんをそれ以上緊張させない」ことが重要になる。リラックスとまではいかなくても、交感神経優位=緊張にならないような体験設計が重要だ。今回は「五感が整う空間デザイン・シリーズ」の第2弾として「香り」を取り上げた。
現代における香りの代表格は「アロマ」ではないだろうか。ホテル、商業施設、個人宅などなど、アロマの香りが活用されている場所は数限りないし、「アロマ」という言葉を聞かない日はないくらい、アロマが現代では浸透している。
では、数あるアロマの香りの中でも「リラックス」という観点で効果が期待できる種類は何になるのだろうか?
内閣府に公益認定された、アロマテラピー関連で唯一の公益法人「AEAJ」の調査によると、リラックスのために多くの機会で活用されているのが、「ラベンダー」と「サンダルウッド」であることが分かりました。

ラベンダーは、主成分である「リナロール(linalool)」「酢酸リナリル(linalyl acetate)」が中枢神経系に作用して副交感神経を優位にすることが分かっています。鼻から吸収された香気成分が**大脳辺縁系(特に扁桃体・海馬)**に作用し、ストレス反応を抑制するともいわれます。
また、サンダルウッドは、主成分の「α-サンタロール(α-santalol)」「β-サンタロール」が嗅覚を介��してGABA受容体やセロトニン経路に作用し、鎮静・抗不安効果をもたらす可能性があるとされます。

著者プロフィール
所長 石田 毅
ウェルネス領域におけるCX(顧客体験)設計とブランド戦略の専門家。スカイスパYOKOHAMAでのコワーキング開発を経て、美容・医療分野の体験価値向上に取り組んでいる。
VoL.48



.png)
![更なる成長の予感!
劇的変化を見せる医療市場[医療ツーリズム編]](https://static.wixstatic.com/media/019307_6766a79cce864f6e80ab1ddab1720943~mv2.png/v1/fill/w_800,h_481,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/Frame%201610%20(2).png)